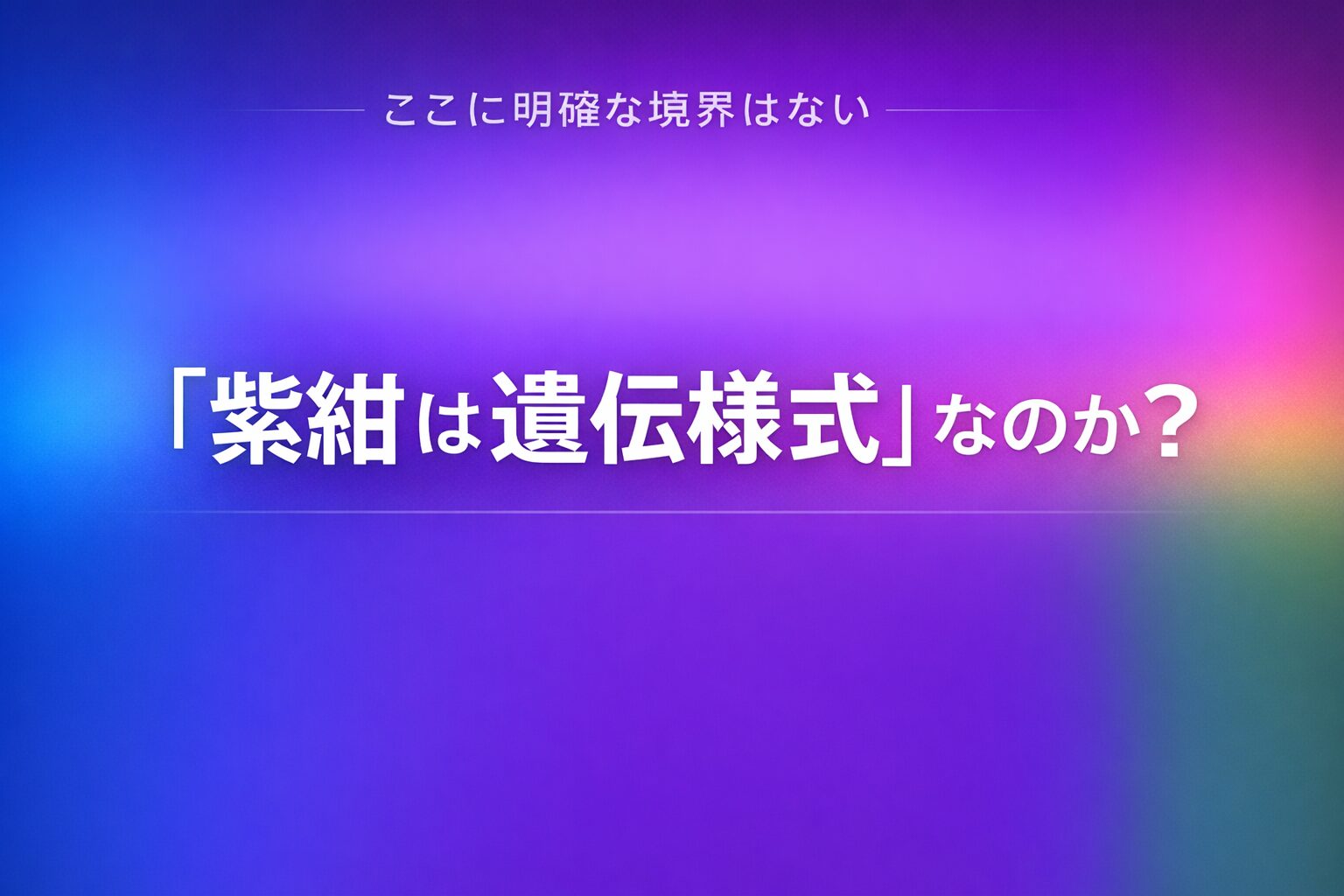— 瑠璃花をブルーと呼ぶことへの指摘を整理する —
SNS上で、
私が管理名として扱っている「瑠璃花」を「ブルー」と表現していることについて、
- ブルーではない
- 紫紺は遺伝“様式”を指す
- だから紫紺の範囲を出ないものは、すべて紫紺である
といった意見を見かけました。
一見すると学術的な主張のようにも見えますが、
用語の使い方や論理の組み立てを確認すると、成立していない部分が多い
というのが私の考えです。
本記事では、その点を整理します。
① 「遺伝様式」という言葉の使い方について
まず確認しておきたいのは、
遺伝“様式”という言葉が、本来どのような概念を指すのかという点です。
生物学における遺伝様式とは、
- 優性・劣性
- 伴性遺伝
- 多因子遺伝(ポリジーン)
など、形質がどのようなパターンで次世代に伝わるかを示す用語です。
したがって、
- 色名
- 見た目の印象
- 表現型の呼称
といったものは、遺伝様式そのものではありません。
▶ 「紫紺=遺伝様式」とする前提は、用語的に成立していません。
② ニジイロクワガタの色は「構造色」

ニジイロクワガタの色は、
色素ではなく、クチクラの多層構造によって生じる構造色です。
構造色では、
- 層間隔
- 配列密度
- 構造の乱れ
- 光源や観察角度
などの条件によって、反射波長が連続的に変化します。
このため、
- 青
- 紫
- 紫紺
- 青寄り
- 紫寄り
といった明確な境界線は本質的に存在しません。
③ 「範囲内を出ない=すべて紫紺」は説明になっていない
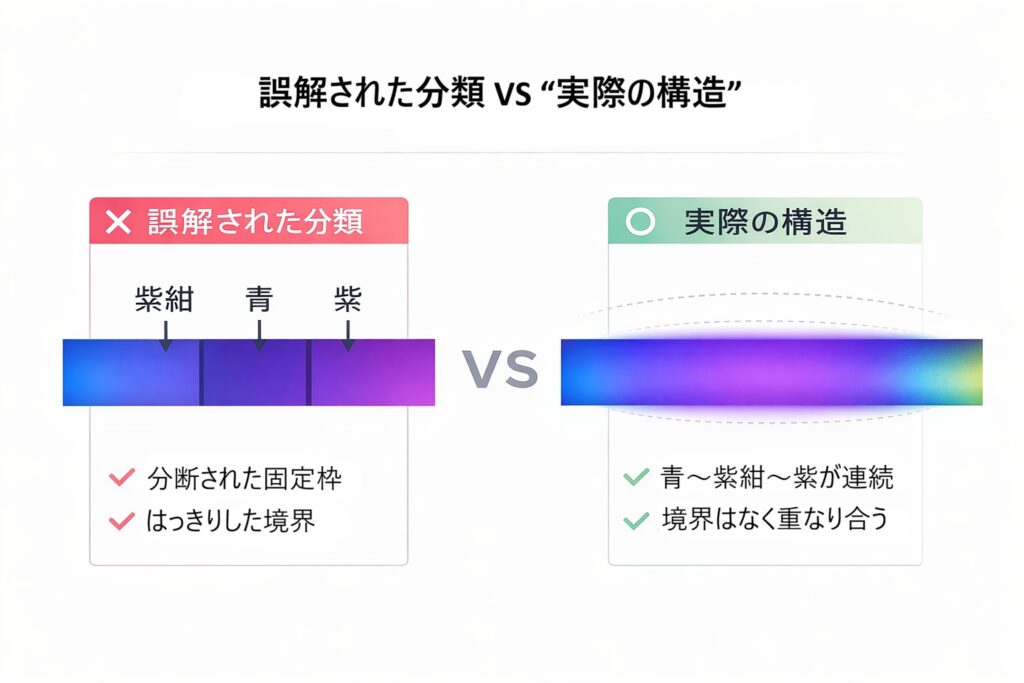
見かけた主張では、
- 紫紺は遺伝様式
- 紫紺の範囲を出ないものは、すべて紫紺
とされています。
しかしこれは実際には、
「紫紺」という言葉の定義を広く取り、その範囲に収まるものをすべて紫紺と呼ぶ
という、分類ルールの宣言に過ぎません。
▶ 遺伝の説明でも、色の成り立ちの説明でもない
という点を押さえておく必要があります。
④ 遺伝するのは「色」ではなく「傾向」
では、なぜ「紫紺ばかり出るライン」が存在するように見えるのでしょうか。
これは、
- 紫紺という“色そのもの”が遺伝している
のではなく、 - クチクラ構造が短波長寄りに形成されやすい
- 構造の乱れが入りにくい
といった形成傾向が、
複数遺伝子と環境要因の組み合わせによって受け継がれている
と考える方が自然です。
これは、いわゆる
量的形質(連続量的な性質)の振る舞いに近く、
- 固定形質
- 単一の遺伝様式
とは異なる現象です。
⑤ 瑠璃花を「ブルー系」と表現する理由

私が瑠璃花を「ブルー」と表現しているのは、
観察角度が変わっても
青の印象が前面に現れやすい
という、見え方の傾向を説明するためです。
なお、写真の個体は、斜めから見ると紫寄りの印象が強く現れる角度があります。
こうした前提を踏まえたうえで、瑠璃花は、
観察角度が変わっても、比較的ブルーの印象が前面に残りやすい個体を中心に選別しています。
これは、
「ブルーで固定されている」
「必ず青になる」
という主張ではありません。
累代したうえでもブルー寄りの個体が出現していることは確認していますが、
それを「固定」や「保証」として表現する意図はありません。
あくまで、観察結果に基づく便宜的な呼称という位置づけです。
⑥ まとめ
整理すると、次のようになります。
✖ 紫紺は遺伝様式ではない
✖ 「範囲内を出ない=すべて紫紺」は遺伝の説明になっていない
◯ 遺伝しうるのは「構造形成の傾向」
◯ 色の呼称は、観察上の便宜的な表現に過ぎない
「ブルーか、紫紺か」という言葉の問題というよりも、
構造色という前提をどこまで共有できているか
という点が、議論のズレを生んでいるように感じています。
*本記事は、特定の個人を批判することを目的としたものではなく、
用語と考え方の整理を目的としています。
▼ 本記事で扱った「色」「固定」「遺伝様式」という言葉は、
生物学・物理学の文脈では慎重な使い分けが求められます。
以下に挙げる文献は、
構造色や多因子的・連続的な表現型を理解するための基礎資料です。
本記事の内容と照らし合わせながら、
各自の視点で検討していただければと思います。